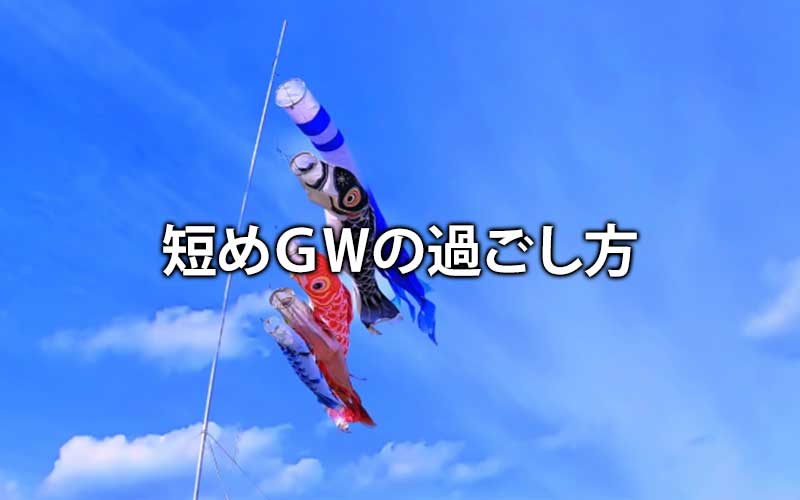花といえば桜を指すように、私たちは桜が大好きです。
春になると桜の話題を聞かない日はありません。
毎日のニュースでも桜前線の進み具合を報じていますし、自分の町の桜はいつ咲くのか、お花見はいつにしようかとそわそわしてしまいますね。
桜を知る
桜は品種が多いことでも知られています。
桜と聞いて多くの人が思い浮かべるのはソメイヨシノだと思います。
整ったかたちの5枚の花びら、うっすらと赤みの差した美しい桜色。
そして一斉に花開く華やかさなど、ソメイヨシノは美しい花を咲かせる品種です。
ソメイヨシノはエドヒガン(江戸彼岸)を母に、オオシマザクラ(大島桜)を父に持つ交雑種であることがわかっています。
しかし、エドヒガンとオオシマザクラをかけあわせてもソメイヨシノを簡単に再現することはできず、さまざまな性質を持った木が生まれてしまうのだそうです。
そのため、ソメイヨシノはすべて接ぎ木や挿し木で栽培されており、日本全国にあるソメイヨシノはすべてクローンです。
もともとが同じ木なので、開花のリズムも揃いやすいのでしょう。
日本の各地に自生しているエドヒガンの中には、樹齢数百年といわれる大木も存在します。
オオシマザクラは日本固有種で、伊豆大島にある古木は特別天然記念物に指定されています。
どちらも長く生きる木です。
一方、ソメイヨシノは両親と違って寿命が短く、60年から80年で枯れてしまう場合もあります。
第二次世界大戦後の復興期に植えられた桜並木などはすでに老木となってしまいました。
大きなソメイヨシノの幹に、直接花が咲いていることがあります。
これは「胴吹き」と呼ばれ、老木に多く見られる現象です。
近くで花を観察できるのはうれしいですが、木が弱り始めている可能性もあり、見かけるとちょっと複雑な気持ちになります。
各地の桜の名所では、ソメイヨシノの若木を植えたり、品種を入れ換えるなどの対応を始めているところもあります。
美しい桜の風景がこれからも見られるよう、木を守っていきたいものです。
桜を歌う
和歌の世界でも、花といえば桜です。
万葉集が編まれた奈良時代はまだ梅のほうが人気が高く、桜を題材とした和歌は梅の約3分の1ですが、平安時代の古今和歌集になるとこの比率が逆転します。
平安貴族たちは桜を好んだようです。
ちなみに、いにしえの人々の和歌に登場するのはヤマザクラです。
江戸時代まで、人々にとってもっとも身近な桜は山野に自生するヤマザクラでした。
そのため、古い時代の和歌では、桜は山や峰といった言葉と一緒に詠まれていることがあります。
現代でも桜の歌は大人気で、「桜ソング」というジャンルがあるほどです。
桜が咲くのは卒業や入学のシーズンで、年度替わりでもありますので、別れや旅立ち、未来への思いをのせた歌詞によくなじむのでしょう。
また、花の美しさや花びらが散る儚さから、桜はラブソングにもよく登場します。
毎年ランキングが作られるほど楽曲数が多い桜ソング、あなたのお気に入りの曲はなんでしょう?
桜を食べる
私たちは昔から、花を愛でるだけではなく食べ物としても桜に親しんできました。
桜の葉を巻いた桜餅や、桜の花の塩漬けにお湯を注いだ桜茶、桜花をかたどった和菓子など、独特の香りや色合いを楽しむことができます。
桜の花の塩漬けはご飯に混ぜても美しいですし、あんぱんに載っていることもありますね。
伝統的な食品にとどまらず、最近はおしゃれなカフェやパティスリーにも桜を使ったドリンクやスイーツが並び、人気を集めています。
また、桜の花や葉が入っていなくても「桜」の名がついているものもあります。
サクラエビや桜鯛、サクラマスは、赤みを帯びた体色や桜の時期に旬を迎えることなどからその名がついたと言われています。
桜肉は馬肉のことで、名前の由来には加熱すると桜色になるからという説があります。
桜でんぶは白身魚を原料に食紅で色をつけた食品で、巻き寿司などに使うと華やかな彩りとなります。
静岡の郷土料理に「さくらごはん」というものがありますが、これは桜の花を混ぜ込んだものとは異なり、具を入れずに醤油で炊き込んだご飯です。
うっすらと茶色い炊き込みご飯の色を桜色に見立てた名前だと言われています。
他の地域では茶飯と呼ばれていますが、「さくらごはん」のほうがなんだかおいしそうに感じます。
寒桜から大島桜、ソメイヨシノに続いて華やかな八重桜と、桜のリレーはしばらく続きます。
花だけでなく、桜にちなんだごちそうを味わうのも春の喜びです。
どうぞ身近な桜を楽しんでみてくださいね。