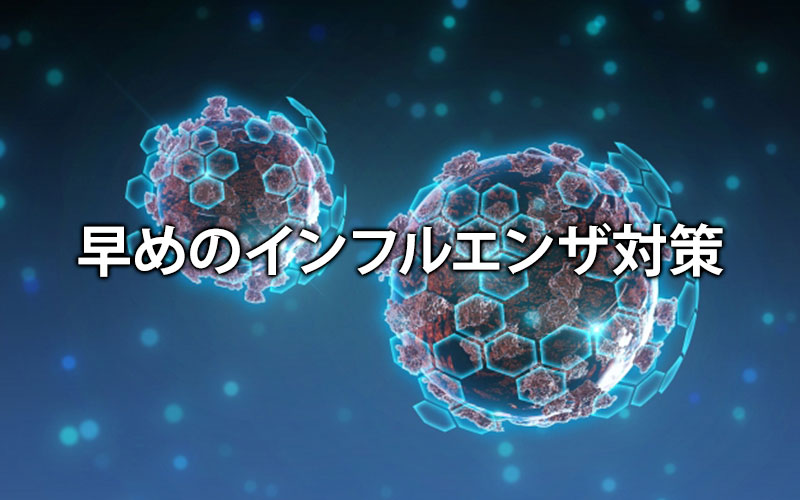にぎやかなセミの声が終わり、秋の夜にはリーンリーン、チンチロリン、ジーッジーッなどさまざまな虫の音が聞かれるようになります。
夏のセミをはじめ、虫が活動する季節には虫の音も聞こえるのですが、「虫鳴く」「虫の音」などは秋の季語。
各地の公園や自然観察施設などで、虫の鳴き声の鑑賞会が開かれるのも主に秋です。
鳴く虫と人々との関わり
自然と親しんでいた時代の人々にとって、虫は非常に身近なものでした。
また、昔の日本家屋は風通し良くオープンな造りでしたので、秋の夜ともなれば虫の音がうるさいほどだったのではないでしょうか。
万葉集にはすでにコオロギが詠まれていますし、平安貴族はさまざまな虫をカゴに入れて音色を楽しんでいたそうです。
江戸時代になると、庶民にも虫の音を楽しむ文化が広がりました。
江戸の町では声の良い虫を売り歩く商売があり、野山で捕まえた虫だけでなく、人工的に繁殖させた鈴虫なども売られていました。
技術の発達により、季節を早めて出荷することも行われていたそうです。
江戸時代の人たちは鳴く虫が大好きだったのですね。
露天や行商での虫売りは第二次世界大戦で一度とだえたものの、戦後すぐに復活し、高度成長期まで続いていたそうです。
今は家庭で鈴虫を飼う人はほとんどなく、昆虫の飼育はカブトムシやクワガタが中心になってしまいました。
それでも、「虫の音」を愛好する人はいまも少なくありません。
広島市森林公園こんちゅう館では9月に「秋の鳴く虫」の企画展が行われていました。
同様の催しは全国各地で開催されています。
小泉八雲も愛した虫の声
虫の音を楽しむ文化は日本だけでなく、世界各地に見られます。
一時期、「虫の音を理解できるのは日本人とポリネシア人だけ、その他の人々にとっては雑音でしかない」という話が信じられていましたが、現在ではこの説は否定されています。
古くは古代ギリシャの人々も虫を飼い、その音色を楽しんだということです。
ギリシャにルーツを持つラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は虫が大好きで、日本で暮らすようになってからもさまざまな虫を飼ったそうです。
中でも八雲は、松虫や鈴虫、草ひばりなどの美しい音色を愛していました。
島根県松江市の小泉八雲記念館には、八雲夫妻が虫を飼っていた竹製の美しい虫かごが残されています。
八雲は、大学の講義で「虫を真に愛する人種は、日本人と古代ギリシャ人だけである」と語ったそうですが、その他の地域でも、人々は虫の音に耳を傾けていたに違いありません。
虫が鳴くことを英語ではsing、フランス語ではchantと表現することがあります。
どちらも「歌う」という意味ですから、単なる雑音としてとらえているわけではないことがわかりますね。
虫の声を文字にする
美しい虫の音にひかれるのは万国共通。
とはいえ、虫の音を擬音であらわすのは日本語が得意とするところと言えるかもしれません。
日本語には表音文字の「かな」があるため、音を表現しやすいということも関係がありそうです。
虫の声を文字にしたものとしてまず思い浮かぶのは、唱歌「虫のこえ」ではないでしょうか。
あれ松虫が 鳴いている
ちんちろちんちろ ちんちろりん
あれ鈴虫も 鳴き出した
りんりんりんりん りいんりん
秋の夜長を 鳴き通す
ああおもしろい 虫のこえ
きりきりきりきり こおろぎや
がちゃがちゃがちゃがちゃ くつわ虫
あとから馬おい おいついて
ちょんちょんちょんちょん すいっちょん
秋の夜長を 鳴き通す
ああおもしろい 虫のこえ
現代でも小学校の音楽の時間に習うので誰でも知っている歌ですが、これほどわかりやすく虫の鳴き声をあらわしているのは見事です。
ちなみに、二番の歌詞に登場する「こおろぎ」は、もともと「きりぎりす」だったそうです。
鳴き声と韻を踏んでいたものですが、きりぎりすはこおろぎの古語のため、昭和初期に現代語に改められたということです。
現代では、虫に親しむ機会は減りました。
それでも、ちょっと意識すると虫の音はあちこちから聞こえてきます。
繁華街はさすがに無理ですが、都市部でもあきらめることはありません。
公園の茂みやビルの植え込み、住宅の庭先でも、虫たちは美しい音色を奏でています。
静かな秋の夜には、ぜひ耳を澄ましてみてください。