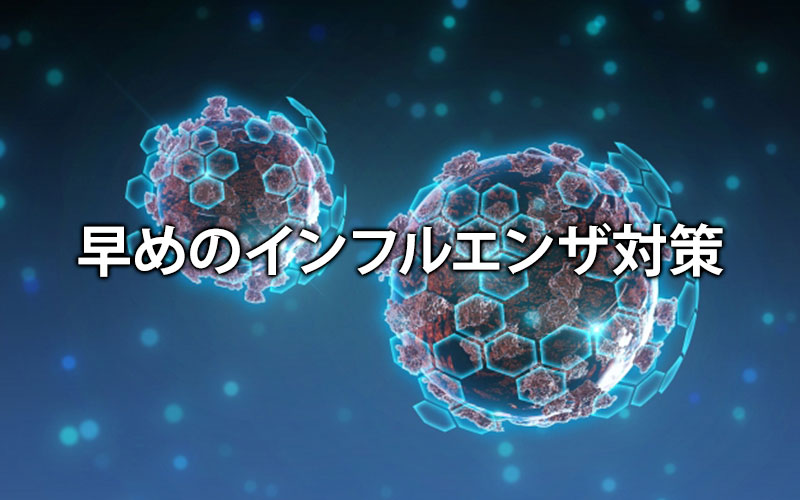秋が深まってくる頃、外を歩いていると、ふと甘い香りに包まれることがあります。
どこからともなく漂ってくるその香りの正体は、キンモクセイ。
鮮やかなオレンジ色の小さな花を枝いっぱいに咲かせ、秋の訪れを知らせてくれる木です。
香りの良い木々
日本には、季節ごとに香りで楽しませてくれる花木があります。
冬のロウバイ、春にはジンチョウゲ、夏にはクチナシ、そして秋にはキンモクセイ。
これらは日本の四大芳香木とされています。
どれもすばらしい香りですが、その中でもキンモクセイはもっとも親しまれているのではないでしょうか。
キンモクセイの花は、例年9月末から11月初め頃にかけて咲きます。
気候によっては、秋の間に二度咲くこともあるそうです。
開花期間はおよそ一週間と短く、雨や風であっという間に散ってしまいますが、その短さがかえって印象的です。
オレンジ色の小さな花が地面に散ったところも美しいですね。
福山市の木・モクセイの仲間たち
キンモクセイはモクセイ科モクセイ属の常緑樹です。
モクセイの仲間には、白い花を咲かせるギンモクセイや、淡い黄色のウスギモクセイなどもあります。
一族の中ではもっとも知名度が高い(?)キンモクセイですが、実はギンモクセイの変種だと考えられています。
モクセイは福山市の「市の木」のひとつでもあります。
キンモクセイだけでなく、他のモクセイにも注目してみましょう。
ギンモクセイも良い香りを放ちますが、キンモクセイよりは花が少なく、やや控えめで上品な印象です。
ウスギモクセイはキンモクセイと葉っぱがよく似ていて、花の色も同じ黄色系統なのでなかなか見分けがつかないことがあります。
見分ける決め手になるのは「実がなるかどうか」。
花のあとに実をつけるならウスギモクセイ、実をつけなければキンモクセイだと考えられます。
キンモクセイに実がならない理由
街路樹や庭木としてよく見かけるキンモクセイですが、その実を見たことがある人はほとんどいないでしょう。
これは、日本で植えられているキンモクセイがほぼ「雄株」だからです。
キンモクセイの原産地は中国南部。
雌雄異株の植物ですが、古くに日本へ渡ってきた際、花つきが良く香りの強い雄株が選ばれて持ち込まれたと考えられています。
中国ではキンモクセイの実も見ることができるそうですが、日本国内には実を結ぶはずの雌株がほとんどないため、花だけで終わってしまうのです。
ちょっと切ないですね。
現在日本にあるキンモクセイの多くは、挿し木で増やされたもので、いわばクローン。
同じく挿し木で増やされるソメイヨシノ(桜)とは異なり、キンモクセイにはいくつもの系統があると考えられますが、それでも実生で増える植物に比べると親戚同士の木が多そうです。
暮らしの中のキンモクセイ
キンモクセイは花を乾燥させて香りを楽しむこともできます。
中国では古くから「桂花(けいか)」と呼ばれ、花を砂糖漬けにしたり、お茶やお酒に加えたりして利用されてきました。
桂花陳酒(けいかちんしゅ)や桂花茶といえば、まさにキンモクセイの香りです。
漢方では、のどの乾燥や咳を鎮める効果があるとされ、香りを楽しみながら体をいたわる植物として親しまれてきました。
キンモクセイの香りはフレグランスにも取り入れられていますし、最近では季節もののハンドクリームやボディソープ、シャンプーなども人気を集めています。
街で見つける秋の香り
キンモクセイは、大気汚染や剪定にも強く、日陰でもよく育つため、街路樹や庭木として全国で植えられています。
数メートルの大木から、一般家庭の生け垣まで、樹形もさまざまです。
北海道などの寒冷地を除けば、日本のほとんどの地域で見ることができるでしょう。
普段はあまり目立たない常緑樹ですが、秋になると甘い香りを放ち、突然存在感を増します。
「こんなところにも植えられていたのか」とびっくりすることがありますね。
この季節、散歩の途中で香りをたどりながら、身近なキンモクセイを探してみてはいかがでしょうか。
同じ地域でも、木が植えられている場所や日当たりによって咲く時期が少しずつ違ったりします。
1本の木の開花時期は短いですが、リレーのようにあちこちの木が香りの主役をつとめるのです。
先週はあちらの道、今週はこちらの公園と、自分だけの“キンモクセイマップ”を作ってみるのも楽しいかもしれません。